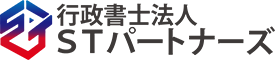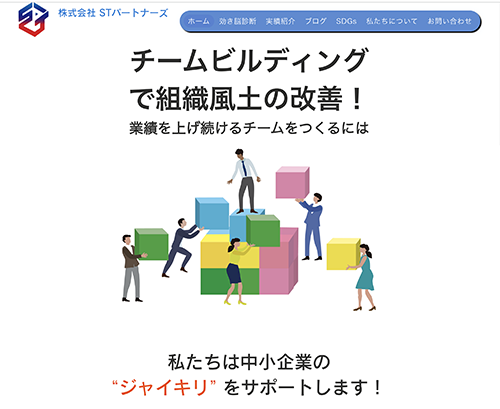第18回社内研修はOKR!
当事務所では、定期的にチームビルディングの社内研修を行なっています。第18回目は、初めて外部講師をお招きし、「OKR」という目標管理手法について一日を通して学びました。今回の研修目標は、自社のOKR1層目を完成させることでした。
今回の講師は、当事務所代表のチームビルディング勉強会の仲間でもある、Forrestの和田祐司さんにお願いしました。和田さんは、体験型研修の講師をされている傍ら、大人と子どもが感じるままに思い切り遊ぶことができる場を提供する「原っぱ大学」の運営に携わっているなど、多彩な活動をされていらっしゃいます。
【OKRとは】
はじめにOKRを簡単に説明します。OKRとは、企業や個人の目標達成を支援するフレームワークで、1970年代にインテルの元CEOであるアンドディ・グローブによって考案されました。 その後1999年にGoogleへ導入され、飛躍的な進歩を遂げたことで広く知られるようになりました。日本でもメルカリなど、ベンチャーやITなどの企業を中心に導入が進んでいます。
大企業向けと思われがちなOKRですが、実は中小企業や小規模事業者でも大変有効な手法ということで、当社でもこの研修を実施する方針となりました。
OKRは以下の2つで構成されています。
OKRとは
・「O」=Objective(目標)
・「KR」=Key Results(主要な成果)
Objectiveは、「何を達成したいのか?」を示す定性的な目標で、チームや個人が目指す方向性を明確にします。
Key Resultsは、「どのように達成するか?」を具体的な指標で測り、数値や期限を設定して進捗を測定できるようにします。
OKRは、会社の目標、チームの目標、そして個人の目標をしっかり理解し共有する仕組みであり、メンバーの一人ひとりが活躍して生産性を上げることにより、目標達成を目指します。
【仮想体験ゲームは成長が見えるから面白い!】
当日のプログラムですが、OKRの基礎知識に関して簡単に説明があった後、「ビジョンタワー」という仮想ゲームを体験しました。
「ビジョンタワー」は、まず、指示役と作業役に分かれます。そして、作業役は目隠しをし、指示役のみタワーの完成形を確認します。その後、指示役が目隠しをした作業役に「言葉だけ」で指示を出し、指定されたタワーの完成を目指します。
結果を申し上げますと、私たちは制限時間内にタワーを完成させることは出来ませんでした!残念・・・
ゲーム後の振り返りの時間では以下の感想が出ました。
ビジョンタワー体験後の感想
作業役からは、
・目隠ししている状況だと指示待ちのロボットのようになってしまった
・自分からもっと質問するべきだった
指示役からは、
・見えない状況がどういう感覚なのか、理解せずに指示を出してしまった
・もっと具体的な表現の言葉を選ぶべきだった
その後、講師からの提案で、全員が目隠しをしていない状態でもう一度チャレンジしてみたら、なんと数分でクリア出来てしまいました。
この仮想ゲームは、チームのコミュニケーションや信頼関係を強化する目的で行わることが多いそうですが、OKRの「O」がどれくらい大事か分かるように和田さんがアレンジしてくれたそうです。メンバー全員が、目的、目標を共有すること、各自が目標達成のためにアイデアを出し協力して動くことが、ともて重要であることが実感できました。
【自社の「O」(目標)設定へ】
午後の部では、OKRの具体的な設定の方法を学び、いよいよ自社のObjective(目標)とKey Results(主要な成果)の設定にチャレンジしました。
OKRは上位の層から下位の層へと順に設定していくというプロセスを踏みます。まずは、事務所が⽬指している「O=目標」を代表から発表、共有することからはじめました。
なお、「O」には、「ムーンショット」と「ルーフショット」という2つの目標設定があります。ムーンショットは、月のムーンが由来で、目標の進捗70%達成でも十分だとするチャレンジ目標となります。対するルーフは屋根。ルーフショットは100%の必達目標となります。
また、目標を決める上では、
・財務
・顧客
・業務プロセス
・学習と成長
の4つの視点を持つことが大切だと講師から説明がありました。
そして、代表が掲げた「O」は、ムーンショットで売上の数字やその期限もチャレンジングな内容でした(スタッフ一同、少々不安に・・・)!
その後、当事務所の「O」としてふさわしいか、メンバーの目標として合意できるのか話し合い、それぞれが自分の考える目標についても共有しました。 想定以上に時間はかかりましたが、最後は出された意見の中から皆が納得する内容を「O=目標」とすることができました。
【「KR」は業務改善のアイデアの宝庫】
「O」を決めた後は、その目標を達成するための「KR」を決めていきます。「KR」は目標の達成度を示す指標となるため、その内容が、
・具体的であるか
・測定可能で検証ができるか
・野心的な設定か(ストレッチが効いているか)
・目的に沿っているのか
・達成までの期間
などが設定のポイントになりますます。
ホームページの集客数、マニュアルの定型化など、普段の業務で改善したらどうかと感じていたことを、各々が付箋に書き出した後、内容をグルーピングし、4つの「KR」に絞り、設定することができました。
この段階で時間がきてしまい、OKR研修の一回目は終了となりました。次回のOKR研修では、4つの「KR」を達成するために必要な2層目のOKRを検討する予定になっています。
【OKR研修はチームビルディングとしても有効】
普段は日常業務で忙しく、事務所のここに課題があると感じていても、手を止めてまで解決に動いてないと感じることも多かったのですが、この研修を通して、改めて業務の課題や改善策について考え、全体で意見を出し合えたことはとても有意義な時間でした。
また、自分以外のメンバーの意見は自分にはない視点と発見があることを改めて新鮮に感じ、チームの仕事に対する真摯な姿勢についても再認識することができました。
会社の目標をメンバーが理解共有し、それに向かい一人ひとりが活躍することで達成を目指す「OKR」という仕組みは、チームビルディングを推進する上では必要不可欠だと感じました。今後、日本の中小企業にもOKRがどんどんと導入され始めるのではないかと思います!
私たち、STパートナーズでは、企業の課題感にあわせた仮想体験ゲームのコンテンツを複数用意しております。まずはチームビルディングがどういう内容なのか話だけでも聞いてみたいというご相談にも喜んで対応いたします。お気軽にお問い合わせください。